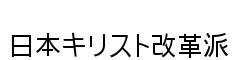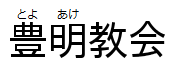2011年2月20日「イエスのために辱められる幸い」(使徒5章33~42節)
18世紀から19世紀にかけてのドイツの神学者シュライエルマッハーは、こう言いました、「主は他の誰に対してよりもガマリエルにこそ、『あなたは神の国から遠くない』と言いたかったろう」と。同じように、古い教会伝説の中には、ガマリエルはこの後、かのニコデモや息子のアビブと一緒に、使徒ペトロやヨハネから洗礼を受けてクリスチャンになった、という作り話があります。確かにシュライエルマッハーや古き伝説のように、ガマリエルを高く評価したい気持ちはよく分かります。何しろ彼のお陰で使徒たちは、死刑を免れたのですから。しかしながら、そのようにガマリエルが使徒たちに好意的であったとするならば、彼に説得されたはずの議会が、なぜ鞭で打つようなことをしたのか、疑問が残ります。よし、分かった、というならば、鞭で打つことなく、先のペトロやヨハネの時と同じように釈放するだけで良かったのではないでしょうか。ここには、表面をなぞっただけでは見えてこない、もっと深いものがありそうです。
今朝の聖書箇所を十分に理解するためには、ユダヤ最高議会サンヘドリンについて、少し詳しく知る必要がございます。既にご存じの通り、サンヘドリンにはサドカイ派とファリサイ派という二つの大きな党派がありました。現代と2000年前のユダヤとをあんまり単純に一緒くたにすることはできませんけれども、敢えて分かり易く言いますと、サドカイ派とファリサイ派とは、ユダヤ最高議会の二大政党なわけです。で、どちらが与党かと言いますと、これはもう圧倒的にサドカイ派なのです。つまり、大祭司を初め、当時の特権階級である祭司たちの政党が、基本的に議会の多数派でありました。一方、ファリサイ派は野党であり少数派です。言い換えれば、時代の流れに乗り、時の権力に迎合してきたのがサドカイ派、反対にいつもそれに否を主張し続けてきたのがファリサイ派ですね。これだけを聞かれると皆さんは、そうするとファリサイ派はほとんど影響力を持つことができなかったということかな、と思われるかもしれませんけれども、実際はそうではありません。数は少なくても、ファリサイ派は民衆の支持を得て、強力な支持基盤を持っておりましたので、多数派のサドカイ派も聞き耳を立てざるを得なかったのです。その中でも特に影響力を持っておりましたのが、今日登場いたしましたガマリエルという律法の教師なのです。この人は、皆さんも知っての通り、パウロの師匠であった人ですが(使徒22:3参照)、私たちが普通想像するよりも遙かに凄い人です。通常、律法の教師は「ラビ」と呼ばれますけれども、ガマリエルだけは違いまして、「ラバン」と皆から敬意を込めて呼ばれました。正確には「ラバン・ガマリエル・ハッザーケーン」と言いますが、意味は「かの長老ガマリエル大先生」です。単なる先生ではない。大先生なわけです。ユダヤ教の古代文献に、彼がどれだけ偉大であったかを物語る文章がありますので、ご紹介したいと思います。次のような文章です、「ラバン・ガマリエル・ハッザーケーンが死んで以来、もはや律法への尊敬はなくなってしまった。同時に、純潔と節制も絶えてしまった」と。彼のようにラビではなくて、ラバン、即ち大先生と呼ばれる律法の教師は、ユダヤ教の長い歴史においても、数人しかおりません。ガマリエルはその偉大な尊称を民衆の間に生み出した初めの人でありました。
さて、このような背景を踏まえた上で、改めて今朝の聖書箇所を呼んでみますと、要するにガマリエルの言ったことは何であったのか、また彼に説得された議会がなぜ使徒たちを鞭で打ったのか、見えてまいります。ついで申し上げますと、鞭打ちというのは、決して軽い刑罰ではありません。申命記25:3・4に鞭打ちについて律法の規定がこのように記されてあります、『もし有罪の者が鞭打ちの刑に定められる場合、裁判人は彼をうつ伏せにし、自分の前で罪状に応じた数だけ打たせねばならない。四十回までは打ってもよいが、それ以上はいけない。それ以上鞭打たれて、同胞があなたの前で卑しめられないためである』と。以前、「パッション」という映画が一般でも公開されて、御覧になった方も多いと思いますが、あの映画の中でイエス様が鞭打たれる、実に生々しい場面がございました。思い出していただくと分かりますが、ちょっとした懲らしめなんてものではありません。まことに過酷な刑でありまして、その余りのことにしばしば受刑者を死に至らしめたのです。
こういった過酷な刑を、どうしてガマリエルに説得されたサンヘドリンは執行したのでしょうか。それは、ガマリエルの発言を丁寧に見ますと、分かってきます。彼は開口一番、『イスラエルの人たち、あの者たちの取り扱いは慎重にしなさい』(35節)と語っていますが、先に言っておきますと、ある種、彼の態度には、実に信仰的な面があることは否定できません。つまり、ある意味で、少し前に使徒ペトロが語りました、『人間に従うよりも、神に従わなくてはなりません』(29節)との弁明を受けて、言わばこう考えたと言ってもよい、即ち、確かにそれはその通りだ、人間の判断は誤りやすい、神の御手に委ねるのが一番というのはその通りだ、と。詩編37:8~9にもこういう御言葉があります、『怒りを解き、憤りを捨てよ。自分も悪事を謀ろうと、いら立ってはならない。悪事を謀る者は断たれ、主に望みを置く人は、地を継ぐ。しばらくすれば、主に逆らう者は消え去る。彼のいた所を調べてみよ、彼は消え去っている』と。言ってみれば、彼はこれを地でやろうとしたわけです。大多数の与党であるサドカイ派の人たちよ、使徒たちに対して怒り狂う気持ちはよく分かるが、感情に任せて行う裁判というのは、誤りやすいものだ、それに憤って裁くと、彼ら使徒たちと同じ穴のムジナということになってしまいますぞ、と。
このように彼の態度は、一面では大変信仰深く、聖書に基づいた態度で裁判を行おうとしているのが分かるのです。激高する議会の頭を冷やすために、憤りの対象である使徒たちを一度退席させたのは、実に賢明な判断と言えるでしょう。こういうところに、彼が大先生と呼ばれる所以もありそうです。しかしながら、一方でまことに敬虔な彼の姿勢も、これを適用する相手がイエス・キリストの使徒たちであったというところに、決定的な誤り、いや致命的と言ってよい間違いがあるのです。ガマリエルは与党の人たちを説得するのに、二つの事例を引き合いに出しました。テウダの事件とガリラヤのユダの事件です。断りもなしに語っているところから、当時の人たちにはよく知られた事件だったと思われます。人々の脳裏に鮮明に焼き付いているのです。特に後者のユダに関しては、『つき従った者たちも皆、ちりぢりにさせられた』(37節)と語られるだけで、先のテウダの従者たちが『跡形もなくなった』(36節)のとは違って、ちりぢりにさせられたものの命脈を保っているのが分かります。実はこれがいわゆる熱心党の始まりと言われているのです。そうです、イエス様の12使徒の一人、熱心党のシモンと呼ばれるシモンがかつて属していたテロ組織ですね。このように多少違いはあるものの、共通している点があります。それは、リーダーがどちらも殺され、滅びてしまった、ということです。ここに、ガマリエルがこの二つの事件を持ち出してきた理由も分かります。つまり、彼が言いたいのは、テウダやガリラヤのユダと同じく、使徒たちの先生であったナザレのイエスも殺され、滅びてしまったではないか、ということなんです。その点では、サドカイ派の人たちと何ら変わりません。サドカイ派の人たちは、死者の復活を否定していますから、その点でイエスの復活を主張する使徒たちを許すことはできませんし、何よりも権力者である自分たちに対して、悪びれもせず非難の矛先を向けてくること自体が許し難いことでした。そのサドカイ派の人たちとは異なり、ファリサイ派の人たちは死者の復活を信じておりますけれども、別の理由で、即ち、律法を守らず、自らを神としている点でイエスを非難してきました。両者はこのように、聖書の理解である教理や神学の点で大いに敵対し合っていたものの、イエス様とその復活、ましてや昇天による王座への就任などを認めない点では一致していたのです。ですから、ガマリエルはついさっき、使徒ペトロが証ししたばかりのイエス様の復活と、天の玉座にお就きになったことには全く耳を傾けず、人間的な判断によって、使徒たちが信じているナザレのイエスは、あのテウダやガリラヤのユダと同じく、殺されていなくなってしまった、そして付き従っているこの者たちも、その内散り散りになるに違いない、だから、サドカイ派の人たちよ、心配はいらない、我々が手を下すことはありません、と主張したわけです。最後に語っている『神から出たものであれば、彼らを滅ぼすことはできない。もしかしたら、諸君は神に逆らう者となるかもしれないのだ』というのは、使徒たちにわずかでも味方しているわけでは毛頭なく、ただ念のために語っているに過ぎません。言いたいのは、怒りの余りやり過ぎて、神の怒りには遭いたくないでしょう、ということです。
このように、一見使徒たちに好意的に見えるガマリエルの発言も、その裏には、イエス様の復活と昇天、着座を全く認めようとしない頑なな心と、あともう一つ、できるだけ全ての人に都合の良い結論を導き出そうという、打算があるのです。普段敵対しているサドカイ派の人たちの気持ちも尊重しながら、我々ファリサイ派の立場も守り、かつ使徒たちとキリスト教会を称賛する民衆にも媚びを売る、これがガマリエルの発言の真意です。死刑にしてしまえば、教会を支持する民衆が黙っていないでしょう。暴動になりかねません。そうするとローマに目を付けられて、厄介なことになります。しかし、民衆の見えないところで使徒たちを鞭打ちにした上で、釈放という形を取れば、少なくとも民衆の目には、使徒たちは無罪放免として映ります。大岡越前の三方一両損ならぬ三方一両得です。こういうわけで、ルカはガマリエルのエピソードを、使徒たちに味方してくれた人の話しとしてではなくて、むしろ、先のペトロとヨハネが単純に釈放された時よりも、一歩も二歩も進んで、鞭打ちという過酷な刑に至るまで、迫害を激化させた張本人として語るのです。次に登場するステファノが、遂に殉教の死を遂げる一歩手前まで来た、ということですね。そして、そのようにして、迫害が厳しさを増す中にあっても、使徒たちは怯えるどころか、『イエスの名のために辱めを受けるほどの者にされたことを喜び』にしたのだ、ということを証しするのです。まさに、これこそクリスチャンにとっての至上の喜びでありましょう。もう以前のように、イエス様のことを三度も知らないと言って否定する者ではなくなっているのです。怖くて部屋の中に閉じこもる人でもなくなっています。今は、イエス様の故にバカにされるなら、いじわるをされるなら、こんなに嬉しいことはない、と思えるようになっている。そこに本当の喜びがあるということが実感できる。苦しいことは苦しいし、辛いことは辛いのだけれども、でもそれを突き抜けて、凌駕して、イエス様にちょっと近づけたということが嬉しいのです。その時、初めて、イエス様がどんなことで苦悩されたか、迫害された時、どのようなお気持ちだったか、ということが、まさに手に取るように分かるのです。イエス様はかつて山上の説教で言われました、『わたしのためにののしられ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪口を浴びせられるとき、あなたがたは幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある』(マタイ5:11~12)と。その時には分からなかったけれども、今ようやくにして、その御言葉の真意が分かったんですね。これが信仰者を支えます。
ガマリエルは八方美人であろうとしたために、かえって真理であるイエス様を否定することとなりました。しかし、使徒たちは、キリスト教会は違いました。わざわざ敵対する必要はありませんが、真理を語るが故の反対は喜んで受け入れるのです。平たく言えば、反対されてナンボということです。真理だからこそ、真理を受け入れない人から反対されるのは当然なのです。イエス様に近い者とされればされるほど、迫害や苦しみは大きくなりますが、喜びと慰めはもっと大きくなるのです。アーメン。