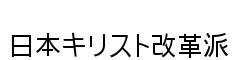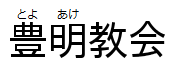2011年3月27日「村八分された人がリーダーに」(使徒7章17~43節)
私たちはいま、使徒言行録に記されたステファノの説教を聴きながら、レント(受難節)を過ごしておりますけれども、きっとステファノの説教には、書かれた文章だけでは伝わってこない凄みのようなものがあったに違いない、と思わされています。御言葉の解き明かしというのは、語る人の存在と一緒になって初めて、真の力を発揮し、神様の御心を十分に伝えるものに用いられます。特にステファノの場合、間もなく処刑されるという、死を覚悟した中で語られた説教ですから、聖霊が最高度に働いて、そこに集まっていた人たちを圧倒したことだろうと想像するのです。
先週、神学校で、ゴー宣教師の指導の下、テモテ指導者訓練会という会が開催されました。たくさんのことを教えられ、様々な訓練を受けさせていただきましたので、時を得て、皆さんと分かち合いたいと願っておりますが、心に迫ってきたことの一つは、「あなたは教会員のために死ぬ覚悟がありますか」という質問でした。参加した若い牧師は皆、「はい」と答えましたし、私も「はい」と答えました。それ以外の答えは考えられなかったですね。その時、今朝の聖書箇所のことを思い出して、そうか、ステファノも死を覚悟して語ったんだな、それだけに彼の信仰がギュッと詰まっているんだな、と感慨深く思ったものです。だとすれば、ステファノの語る旧約の出来事が、単に旧約の出来事を要約するだけで終わっているはずがありません。これも、テモテ指導者訓練会で改めて教えられたことですが、信仰というものは、頭の知識に留まるようなものではなく、行いを伴ってこそ、真の信仰となるのだ、ということです。私自身、生まれたときから教会に通って、CSなどでたくさん聖書の話を聞いてきまして、知識としては頭に詰まっているのですが、それが本当に意味を持ってくるのは、随分後のことで、大学生ぐらいだったような気がします。いろんな悩みや挫折の中で、神様が生きた神様、私の神様になったんです。それまで、それこそ紙の上の神様でしかなかったのが、目の前に生ける神様として立ち現れてきた、言い換えれば、私という人間の人生にとても関わりのある方になったわけです。ユダヤ人たちも同じで、モーセの律法は小さい頃からみんな聞いて、誰しもが知っているのですけれども、それが生きたものになっていない。形だけのものになってしまっている。だから、モーセの生き方や信仰についても、物語としては知っているし、彼が教えてくれた律法も誇りにしているのですが、モーセのように生きようとはしていませんでした。もし、モーセのように生きようとしていれば、イエス様が登場した時、ああ、モーセのような人だ、と思わずにはおれなかったことでしょう。それが即ち、ステファノが言いたかったことです。イエス様が登場した時、ユダヤ人たちはなぜ彼を迫害し、殺そうとしたのか。それは、結局、ユダヤ人たちが、旧約に書かれているモーセの生き様を、本当には分かっていなかった、その通りに生きようとはしていなかった、ということなのです。
御言葉に仕える、御言葉を与えてくださる神様に仕えるということは、牧師や教会役員に限らず、クリスチャンであるならば誰でも、決してモーセ以上に出ない、イエス様以上に出ない、ということです。モーセやイエス様は神様の故に迫害を受けたが、私は受けたくない、これではイエス様について行っていることにはなりません。苦しみや悲しみは誰もが避けたいものですけれども、でも、苦しみや悲しみを通してこそ、私たちはイエス様に近い者にしていただけますし、イエス様のことが本当によく分かるようになるのです。そうでなければイエス様は、『自分の十字架を背負って、わたしについて来なさい』とは言われなかったことでしょう。イエス様が与えてくださる幸いは、苦しみの中でこそ豊かに味わうことができるのです。ステファノはそのことを伝えるために、分かり易くモーセの生涯を三つの段階に分けて語っています。第一期は、生まれてから40歳まで、第二期は、40歳から80歳まで、第三期は、80歳から天に召される120歳までです。ユダヤ人たちが尊敬するモーセはそれぞれの時期、どんな歩みをしたか、思い出してみよう、というのです。そのことによって、自分たちの聖書理解と信仰の持ち方が如何に偏見に満ち、知ったかぶりであり、真理に逆らうものであったかが分かるはずだと。でも、ステファノがこんな厳しいことを言うのは、私たちを落ち込ませたり、いじめたりするためではなく、むしろ真の信仰へと励ますためなのです。
まず第一期ですが、アブラハムの話からモーセの話へと移る17節において、ステファノは『神がアブラハムになさった約束の実現する時が近づくにつれ』と語ります。この言葉がとても重要です。私たちの人生や世界の歴史にどんな出来事が起きようとも、それはすべて神の約束が実現していく過程である、と信ずるのです。目に見える現実は、それとは正反対に見えるかもしれない。モーセの時代、人間的に見れば、事態はますます悪くなるばかりでした。生活はどんどん苦しくなる。生きることさえ否定され、ままならなくなるような時代、次の世代を担う幼子がこの世の権力や悪魔の力によって、命を奪われてしまうような時代、しかし、そこでこそ神の約束は間違いなく実現し始めていたのです。それはどのようにしてか。また、どこにおいてであったか。ステファノの時代のユダヤ人にとっては受け入れがたいことかもしれませんが、民が増え広がったのはエルサレムではなく、忌むべきエジプトにおいてでした。しかも、幼児虐殺の中で、神の御手によって命を守られ、生き延びて、後にイスラエルの民を導くことになるモーセは、あろうことか、ユダヤ人の宗教教育ではなく、エジプト人の教育を受けたというのです。神の律法を知るはずのない民の教育を受けたものが、正規のユダヤ人の教育を受けてない人間が、民の上に立つものとなった。イエス様もそうでしたね。故郷ナザレの人々は、口々に言いました、『この人は、このような知恵と奇跡を行う力をどこから得たのだろう』(マタイ13:53)と。このように、神様の御心に適う信仰は、単なる聖書知識で培われるものではありません。見た目に異教的・この世的であり、教会の常識に反するようであっても、そこに神様の思いを見て取ることが、凄く大切なのです。異教的なことやこの世的なことが良いというのではありません。そうではなく、かえって、自由にダイナミックに御業をなさる神様を、私たちの方が自分たちの常識の中に閉じこめているだけなのです。その殻を破って、神様の御業をそのままに仰ぎ見、従うなら、私たちは主の大いなる御業を見ることができることでしょう。
さて、次に第二期に移りたいと思いますが、40歳になったモーセは、仲間たちのためと思ってやったことが、必ずしも仲間たちに歓迎されるわけではないことを知りました。これは私たちが互いに経験していることではないかと思います。神様のため、兄弟姉妹のため、救いのためと思って、心に思い描いたことが、いつもいつもみんなに喜んでもらえるわけではない。もちろん、自分勝手な思いつきとか、自己満足などの場合は、そういう反応が返ってきても、それはむしろ当然のことなんですが、本当に良い意図と目的であったとしても、否定されることもあるということです。これは私たちに、心からの悔い改めを促すと同時に、大いなる慰めを与えてくれます。心からの悔い改めというのは、教会の中で誰かが語ったり、行ったりしていることについて、妬みの思いや自己中心の思いの故に、知らず知らずの内に、時には意図して妨害してはいないかと恐れるからです。一方、大いなる慰めだというのは、自分が愛の心から言ったりやったりしてことについて、兄弟姉妹から非難されることがあったとしても、それですぐに、自分が悪いと思う必要はない、ということです。天狗になっては困りますが、反対されることを恐れる必要はないのです。全く罪のないイエス様でさえ、多くの人々から非難され、邪魔者扱いされたのならば、主に従う人が非難や妨害に遭うのは、少しも不思議ではありません。誰もが一番になりたいものです。弟子達も誰が一番偉いかと議論しておりました。そんな中で、一人が突出すると、出る杭は打たれるという諺通り、民を主の道に導こうとする人の足を引っ張ろうとしてしまいますね。そのことを素直に認められるか否かが、主の御心に適うかどうかの分かれ道だと言えましょう。ステファノの時代のユダヤ人は、モーセのことを尊敬はしていても、まさか自分たちがモーセを非難し、足を引っ張っているとは全く考えていなかったことでしょう。でも、それに気付くことがとても大事なのです。
第三期は、80歳になったモーセが、指導者としての召命を受けるところから始まりますが、神様がどんな人を、御自分の僕としてお用いになるかが、この出来事を通してよく分かります。神様に声を掛けられた時のモーセは、ファラオの偉大な王子としてのモーセではなく、むしろ人殺しの廉で仲間からもつまはじきにされた、まことに落ちぶれた人、人生失格者としてのモーセでありました。ユダヤ人社会からは遠く離れて、ひっそりと細々と暮らす人でしかなかったのです。そんな人を神様は用いてくださる。実に神様の召命は、人の思いや常識を遙かに越えておりますね。しかも、この人生負け組のモーセをお選びになった神様は、どんな方かと言いますと、声はすれど目には見えない御方でありました。ステファノは意図的に31節で書いています、『もっとよく見ようとして近づくと、主の声が聞こえました』と。エルサレム神殿という絢爛豪華な建物に酔いしれているユダヤ人にとっては、これは驚くべき事ではないかと思います。もちろん、ユダヤ人たちだって、神様が目に見える御方だなどと信じているわけではありませんが、でも、何か形有る物でそれを象徴したいという誘惑には勝てませんでした。それが幕屋であり神殿であったのです。確かに幕屋も神殿も、神様御自身がその設計と建立をお命じになったわけですが、それはあくまで山で示された型、モデルに過ぎないのであって、本来の意図はそこにはないのです。その証拠に、神様がモーセに現れた時、神殿や祭具などの目に見えるものがあったか、ただ主の御声が聞こえただけではなかったか、とステファノは問うております。この目に見えない生ける真の神様の御言葉を伝えるべく立てられたモーセに、人々は聴こうとせずに、かえって自分たちの手で造ったものに安心感を見出そうとしたのです。ここに、私たち人間が生み出す信仰の偽善性が、浮き彫りになっています。目に見えず、手で触れない神様では安心できない。物足りなくなってくる。どうしてもシンボルとなるものを造り、祀りたくなってくるのです。ですから、神様は42節で言われます、『イスラエルの家よ、お前たちは荒れ野にいた四十年の間、わたしにいけにえと供え物を献げたことがあったか』と。いま私たちは荒れ野にいると言っても良いでしょう。被災地にいる人々は現実に荒れ野で生きておられる。そういう中で、むろんクリスチャンならば礼拝を捧げて歩みを進めていきます。献金や献品を献げて、神様に感謝を表し、困っている人々を助けようとしています。でも、だからこそ、私たちは、これからの荒れ野の四十年と呼んでよいであろう、長い復興の歩みにおいて、目に見える何かにではなく、形有るものが再建されていくことにでもなく、目には見えないが生きておられる真の神様と、御自身の尊い命を献げてくださったイエス様とに目を注ぎ、この御方の御心に用いられるものでありたいと、心から祈り願うのです。アーメン。