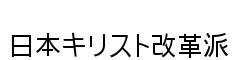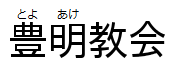2011年4月17日「神の弱さが私を強くした」(第1コリント1章18節~25節)
『十字架の言葉は、滅んでいく者にとっては愚かなものですが、わたしたち救われる者には神の力です』。Ⅰコリント1:18のこの御言葉は、コリントの信徒への手紙第一を代表する御言葉と言ってもよいでありましょう。『十字架の言葉』、この物言いは聖書でここにしか登場しない珍しい表現ですけれども、キリスト教の福音を見事に言い表しております。即ち、十字架につけられたイエス・キリストこそ私たちの救い主であるという、福音です。
十字架ということで私たちがすぐに思い起こしますのは、神の御子であるイエス様が私たち罪人を救うために、身代わりとなって十字架に死んでくださった、というメッセージではないかと思います。簡単に言えば罪の赦しということですね。しかしながら、今朝の聖書箇所、Ⅰコリントにおきましては、罪の赦しということは語られませんで、むしろ、知恵との関連で十字架が語られています。これはある意味、大変興味深いことと言えます。ユダヤ人にとって大事なのは、モーセの律法であり、神殿にまつわる清めの問題ですが、一方ギリシャ人にとって大事なのは、いわゆる知恵であったわけです。その場合の知恵というのは、単なる生活の知恵というものに留まらず、むしろ、奥義と言った方がそのニュアンスが伝わるかもしれませんけれども、世界の奥深い秘密や本質を悟ることをギリシャ人たち、特に哲学者たちは追い求めていたのです。この傾向は、コリント教会のクリスチャンたちにも広まっておりました。言ってみれば、クリスチャンになるということは、ギリシャの哲学者たちに優る知恵を手に入れることだ、と考えていたわけです。ソクラテスやプラトン、アリストテレスのような大哲学者でさえも及ばないような崇高で奥深い知恵がここにある。それに魅せられて、クリスチャンになった人々もいたようです。ある面では、確かにギリシャの哲学に遙かに優るものがあるというはその通りで、そして本当の意味で分かっていれば何も問題はないのでしょうが、コリントの信徒たちの場合、それはむしろ、善くない結果を生み出していたのです。具体的に言いますと、今朝の聖書箇所の前に書いてあります、分裂の問題です。
問題や課題が山積みのコリント教会においても、まず筆頭に挙げられたのが分派の問題でした。パウロ派、アポロ派、ペトロ派、キリスト派と幾つにも教会が分けられてしまっていました。コリント教会という教会は、他の教会に比べましても、偉大で有能な使徒や指導者に恵まれた教会でありました。それがまた誇りでもあった。しかし、個性豊かな先生たちであっただけに、それぞれの信奉者をも作ってしまったのです。結果として、分派ができてしまいました。そのことが如実に現れているのが、洗礼のことです。わたしはあの先生から洗礼を受けた、自分はこちらの先生の味方だ、と各々支持する先生が違ってくる。そんな状況だったものですから、使徒パウロは言ってみれば、私はできるだけたくさんの人に洗礼を授けて、自分の信奉者、自らの党派を作るためにイエス様から派遣されたわけではない、かえってそのような傲慢を打ち砕くものとして十字架を宣べ伝えるために遣わされたのだ、と言わねばならないほどでした。このように、主イエスの十字架というものは、抽象的なものでも、単なる観念でもなく、極めて具体的、日常的なことに関わってくることなのです。十字架につけられたイエス・キリストを信じているのに、教会の中に分裂がある、というのは、大きな矛盾に他なりません。イエス様を信じるということは、生まれ育ちや考え方が全然違う人たちが、一つに結び合わさるということなのです。それができていないということは、本当の意味でまだイエス様の十字架が分かっていない、ということでありましょう。
だからこそ、使徒パウロは『十字架の言葉』を語るのです。ここで言う『言葉』というのは、単なる言葉ではなく、ヨハネ福音書で有名な「ロゴス」のことです。日本語にこだわって言えば、「葉」のつかない「言」、即ち、見ゆる世界を生み出した宇宙の大本の真理であって、ギリシャ人たちはまさにこれを追い求めて、思索を重ねてきたわけです。しかし、そのような思索や探求は、真に真理を掴むことができたか。否!十字架につけられたイエス・キリストを拒んでしまったが故に、かえって真理から遠い者となってしまったのです。そしてそれが故に、主にある兄弟姉妹たちの間を引き裂くようなことになってしまった。その原因はどこにあるか。誰かに責任をなすりつけたら良いのか。もっと和を大事にしたらよいのか。そうではありません。コリント教会に起こった分裂騒動を前に、パウロは人間的な解決方法を全て捨てて、ただひたすら十字架につけられたイエス・キリストに立ち帰るようにと、御言葉の解き明かしを致しました。教会内にごたごたが起きますと、すぐに出てくることは、自分の意見を主張することです。自分が如何に間違っていないかを相手に分からせてやろうとすることです。あるいは、自分なりの解決方法を押しつけようとすることもそうでしょう。とにかく皆、自分を中心に物事を進めようとする。神様さえも自分の味方につけようとするのです。
ここでこそ聖書は言う、そのようなあなたがたの自我が打ち砕かれるために、イエス様は十字架に架かられたのだと。いや、頑なに自己を弁護しようとするあなたがたのために、イエス様は自らが砕かれてくださったのだと。自分を主張することなく、ひたすら父の御心に喜んで仕えられたキリストが見えないか、というパウロの声が聞こえてきそうです。これらのことを語る時に、何よりも先ず大事なのは、このことを語っている私自身が、十字架の主イエスを退けていないだろうか、ということです。パウロは21節で、『そこで神は、宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうと、お考えになったのです』と語っています。『宣教という愚かな手段』と訳されている言葉は、元はもっと単純で「宣教の愚かさ」です。おそらく、こちらの直訳の方が、パウロの意図をうまく表現しているだろうと思います。と言いますのも、「宣教の愚かさ」という物言いには、二つの意味が重ね合わさっているからです。一つは、宣教の中心的な内容である、十字架につけられたイエス・キリストという、人間的に見て愚かでしかないもの。もう一つは、その十字架につけられたイエス・キリストを宣べ伝える宣教自体、人間的に見て必ずしも成功するわけではない、かえって反対に遭い、迫害を受けることの方が多い、という愚かさです。
彼は2:3で『そちらに行ったとき、わたしは衰弱していて、恐れに取りつかれ、ひどく不安でした』と書いていますが、簡単に言えばパウロはこの時、伝道に失敗していたわけです。今までのように伝道が成功して、多くの回心者が与えられるということがないばかりか、良かったと思っていたことが、かえって悪い事態をもたらしてしまったこと、つまり、伝道の成功がむしろ人々の妬みを引き起こしてしまって、それ以降の伝道ができなくなってしまう、という辛い体験をせねばならなかったのです。私は有能な牧師だ、よく出来る伝道者だという自負は、粉々に打ち砕かれました。しかし、そのような絶望と無力感の中にあって、神様御自身が救いの業を進めていてくださったのです。全くの失敗だと思っていたのに、実に不思議な仕方で神様が救われる人を起こしてくださいました。こうやれば必ず伝道はうまく行くというようなマニュアルがあるわけでもない。これが成功を妨げていた原因だと必ずしも断言はできない。そのような人間の知恵、賢さを遙かに越えて神様は、人間の失敗と惨めさと無力感の中で、救いを成し遂げてくださるのです。これこそ人間の知恵に遙かに優る神の力と言わずして何と言いましょうか。ここで聖書は、人間の知恵に対して、神様の知恵を持ち出そうとはしていません。人間の知恵に対しては、神の力、いや十字架につけられたイエス・キリストという弱さを持ち出しているのです。皆さん、キリストの福音は、単なる哲学でも教えでも道徳でもありません。実際に、人を救ってしまうことのできる神の力なのです。しかも、神と人間とに見捨てられ、呪いの木に架けられたイエス様が、この世的に見て、必ずしも成功しておらず、幸福でもなく、しばしば人生の脱落者と思われる人々に信仰を与えてしまうことによって、知恵や知識を自慢し、自らを誇ろうとする人々の自我を打ち砕いてくださるのです。私の自我もまた、あの十字架で打ち砕かれる。そう、私の自我もイエス様と一緒に十字架に釘付けにしてもらえる。
そうしたとき、哀歌が物語る暗く暗澹たる嘆きの言葉も、光を放ち始めます。実際に十字架につけられたのは、イエス様でありましたが、私の自己中心な思い、人間を誇ろうとする自我が、十字架につけられたイエス様の隣に置いてもらうことによって、『あなたは激しく憤り、わたしたちをまったく見捨てられました』(哀歌5:22)という嘆きを、心の底から嘆くことのできる場所が与えられたのです。なぜなら、『わが神、わが神、なぜわたしをお見捨てになったのですか』(マタイ27:46)とイエス様は十字架上で嘆かれたから。そして、腹の底から魂の叫びとして嘆いたその嘆きが、そこで終わることはなく、復活の命の躍動へと至ることを私たちは知っているからです。アーメン。