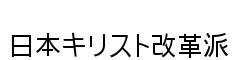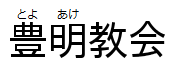2011年7月24日「いつでもどこでもイエス様」(使徒11章19~30節)
使徒言行録は、11章19節を境にして、福音宣教の舞台をエルサレムからアンティオキアへと移します。「移します」という言い方ができるほど、アンティオキア教会は急激な成長を遂げ、異邦人伝道の一大拠点、また母教会となったのです。それはすべて、21節にありますように、『主がこの人々を助けられた』からでした。アンティオキアと聞いても、いまいちピンと来ない人もいるかもしれませんね。私も以前はそうでした。CS時代に聞かれたとしても、たぶん答えられなかったと思います。しかしながら、アンティオキアという町は、ローマ帝国において、ローマとエジプトのアレキサンドリアに続く世界第三のマンモス都市だったのです。人口およそ50万と言われ、「東方の女王」「麗しのアンティオキア」と呼ばれたものです。そういう都会にはみんな憧れて、世界各地から移り住んでくる人たちも多かったと思われます。実際、今朝の聖書箇所に書かれてある通り、地中海に浮かぶキプロス島から来た人もいれば、北アフリカのキレネから移住してきた人もいたんですね。地方では土着の宗教や親類縁者の絆に縛られがちですけれども、アンティオキアのような大都会では、それこそしがらみから開放されて、自由な雰囲気がみなぎっておりますから、ユダヤ人以外の人にもイエス様のことを話そうなんていう冒険もできたのかもしれません。いずれにせよ、アンティオキアは巨大都市ですから、自由と希望に満ち溢れている人がいる一方で、欲望が渦巻き、暗黒と闇に落ち込んでしまう人も数知れずおりました。そんな中で、やはり本物の宗教と言いましょうか、真の神、真の救い主を求める人々も多かったことでしょう、たくさんの人々が救われました。4世紀の名説教家クリュソストモスによれば、奴隷や子供も除いても約20万人、主な教会員だけでも10万人はいただろうということです。かなりのパーセンテージですね。伝承では、著者のルカ自身も、アンティオキアの出身だったようですから、それだけに思い入れも強かったのではないかと思われます、いよいよ私の故郷、母教会の話をすることができると、興奮したかもしれません。
さて、このような世界第三の大都市における伝道の成功を聞きつけて、エルサレム教会は「我関せず」という態度を取ることもありませんでしたし、「勝手なことをやるな」と止めさせることもありませんでした。素晴らしい神の恵みだと感謝して、最も適任のバルナバを派遣したのです。ここにエルサレム教会の懐の深さと思慮深さを見る思いがいたします。エルサレム教会は、大都会アンティオキアに人を遣わすことで、主にある開かれた交わりを持とうとし、またこれを教会の正式な活動と位置づけようとしました。それは彼らが孤立しないためでもあります。そのために立てられたバルナバは、使徒ではありませんでしたが、こういう立場や種類が違う人たちを結びつけるのには、うってつけの人物です。かつて迫害者サウロが回心した時も、サウロと教会とを結びつけたのはバルナバでした。しかも、バルナバは地中海に浮かぶキプロス島生まれの人でしたので、同じキプロス島出身の人がいるところで奉仕するのに、これ以上の人は考えられません。現実問題として、アンティオキア教会の成長にとって、バルナバという人の貢献は、筆舌に尽くしがたいものがありますね。この人がいなかったら、おそらくアンティオキア教会はここまで大きくなれなかったと思います。アンティオキアで救われた多くの人々は、バルナバの信仰からたくさんのことを学んだことと思うのです。そのバルナバが繰り返し教えましたのは、23節にあります通り、『主から離れることのないように』ということでした。私たちの場合も、いろんなことを考えます時に、信仰者になることよりも、またある一時、信仰者であることよりも、ずっと信仰者であり続けることの方が遥かに難しいように思いますね。Ⅰヨハネ2:28にも『御子の内にいつもとどまりなさい』というみ言葉がありますが、まさに、バルナバはそのことの大切さをよく知っていて、救われたばかりの人々に、ひたすらこの方の内に留まるように、離れないようにと慰め、励ましたのです。
しかし、そんなバルナバでも、なかなか一人でこれだけ多くの兄弟姉妹たちを教え、導くのは至難の業です。救われる人々が増えてくるに連れ、バルナバは良き同労者を必要としました。ここで誰を選ぶかは、とても重要な判断です。初めからサウロと心に決めていたかどうかは定かではありませんが、祈りの中でサウロこそ最も相応しい同労者と確信して、彼を捜しにタルソスまで行きました。捜索の「捜」という字が使われていることからも分かるとおり、言ってみれば必死に捜索したのです。相当な労苦があったものと想像できます。故郷タルソスに戻っていたサウロがどうであったか、その様子は書いてありませんけれども、言わば世間的に言えば、ユダヤ人社会に楯突いた男です。以前と同じように故郷で暮らせるはずも無く、孤立無援の肩身の狭い生活をしていたであろうことは、想像に難くありません。それでも必死に喜びを持って、主イエスの福音を伝えていたことと思いますが、このサウロが働くべき場所はタルソスではない、ここアンティオキアであるとバルナバは信じたのだと思います。バルナバは、サウロが神様から召しを受けた時、どんな言葉で語りかけられたか、よくよく知っていたことでしょう。サウロが天上の主イエス様から受けた使命は、異邦人に主イエスの名を伝えることだったのです。そうであれば、今まさに多くの人が救われているここアンティオキア以外のどこで、サウロは働くというのでしょう。バルナバに説得されるようにして、サウロはアンティオキアに赴き、一緒にアンティオキア教会の教会形成と信徒訓練に身を捧げました。
『このアンティオキアで、弟子たちが初めてキリスト者と呼ばれるようになった』と26節に記してありますが、逆に言えば、それだけ世間の人たちや社会に認知されるほどまでに、キリスト者が増えたということですね。つまり、単にそういうあだ名が付けられたというに留まらず、「キリスト者」という名前で一括りにできるような一群のグループがいると、みんなが知るに至ったということなのです。ある意味で、ユダヤ人やユダヤ教に帰依した人でなければ分からないような「キリスト」という言葉が、社会的にも通用するようになったということでもあります。ここから「キリスト教」という言い方も生まれたのではないかと思います。このキリスト教を信じるクリスチャンたちの特徴は、27節以下によく表れております。27節にはこう書かれてあります、『そのころ、預言する人々がエルサレムからアンティオキアに下って来た』と。これは単に預言する賜物を持った人がやって来た、というだけでなく、エルサレム教会とアンティオキア教会との交流が活発になって、預言という賜物においても、若きアンティオキア教会を支援しようということなのです。ここに出てくるクラウディウス帝の治世には、飢饉が何度もあったことが歴史の書物からも知られていますけれども、そのとき生まれたばかりのアンティオキア教会は、早速、母教会であるエルサレム教会支援に乗り出しました。しかもそれは、強制でも画一的なものでもなく、『それぞれの力に応じて』なされた自発的なものであったのです。このように導いてくださった主の御名をほめたたえずにはおれません。私たちも、異邦人教会の母教会であるこのアンティオキア教会に連なる者であることを、心から主に感謝したいと思います。アーメン。