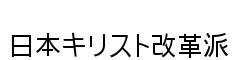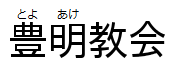2016年1月3日「安息日の祝福」(ルカ6章6-11節)
「また、ほかの安息日に、イエスは会堂に入って教えておられた。そこに一人の人がいて、その右手が萎えていた。律法学者たちやファリサイ派の人々は、訴える口実を見つけようとして、イエスが安息日に病気をいやされるかどうか、注目していた」(6~7節)。
律法学者たちやファリサイ派の人々の安息日のきまりでは、命にかかわる病の場合は安息日でも治療してよいが、そうでない場合はしてはいけないことになっていました。ですから右手の萎えた人を癒すのは安息日にはしてはいけないことになります。もしイエス様が、日付が変わる日没まであと数時間待ってから癒されるなら何も問題にならなかったはずです。ところがイエス様は皆の見ている前でこの人を真ん中に立たせて、その場で癒されたのです。わざわざ相手を挑発するようなとても大胆で、激しいなさり方です。
律法学者やファリサイ派の人たちは律法を正しく守ろうとするあまりに、安息日にしてはいけないこととしてもよいことを具体的に細かく考えました。彼らは「七日目は、あなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない」という言葉に注意を払いました。ですから彼らの安息日についての考えでは、あれもしてはならない、これもしてはならない、ということになります。これでは安息日に何かして律法に違反するよりは、何もしない方が良いということになってしまいます。彼らはその決まりを守ることに熱心でした。しかしこれではきちんと守れたかどうか、いつもびくびくしている窮屈な信仰生活になってしまいます。常に自分は律法に違反していないだろうかと心配になるからです。彼らの心には律法を立派に守ることで神様から祝福を得られるけれども、きちんと守らなければ神様の祝福は受けられない、という思いがありました。違反しないようにしなければならないという強迫観念で自分を縛っているような状態です。そのために人を見るときには、この人はこうあるべきだ、これではいけない、という目で見るようになってしまいます。ですから彼らの目には、イエス様は自分達が大切にしているものをないがしろにする人であり、そうであるのに人々に歓迎され喜ばれている「放っておけない存在」に映ったのです。この出来事はそんな中で起こりました。
「手は元どおりになった」(10節)とありますからこの人の手が萎えたのは生まれつきではなく途中で何かの原因でそうなってしまったと考えることができます。だとすれば右手が途中で使えなくなり、そのことで仕事を失ったかもしれません。どれほど不便をし、つらい思いをしてきたことか想像することができます。
律法学者やファリサイ人たちの安息日の守り方では、このような癒しと慰めを必要としている隣人を見失ってしまいます。彼らにとって右手の萎えた人は、イエス様を訴える口実として利用できればよいのです。イエス様は、悲しみと苦しみをかかえ、慰めと癒しを必要としているこの人を見ようとしないあなたがたの敬虔な信仰生活とは一体何か、これでよいのか、と問いかけたのです。
さらにイエス様は問いかけます。安息日に律法で許されているのは善を行うことか、悪を行うことか。命を救うことか、滅ぼすことか。ここには何もしないという選択肢はありません。律法学者やファリサイ派の人たちにとって安息日にしてはいけないことは「何もしないこと」が安息日律法を守ることでした。しかしそれはイエス様に言わせれば「悪を行うこと、命を滅ぼすこと」なのです。今ここにいる右手の萎えた人には、神はあなたを愛しておられると告げなければなりません。それを安息日が終わるまで待ってからでは、神様の愛は伝わらないのです。だからわざわざ彼らの前で、安息日にもかかわらずその場で癒されたのです。こうして右手が萎えていたこの人は、自分が神に愛され、救い主が自分をしっかりとらえて下さっていると信じることができるようにされました。そしてこのような神様の祝福にあずかることが、安息日の本来の意味なのです。
イエス様の行動は律法学者やファリサイ派の人々の激しい怒りを引き起こしました。イエス様は、彼らのしていることを「悪を行うこと」と断言されました。彼らは怒り狂ってイエス様を何とかしようとしました。これが結局イエス様を十字架につけることへとつながります。イエス様はそうなることがわかっていながら、右手の萎えた人を癒されました。ご自分を十字架の死に渡してでも、この人を安息日の祝福に招き入れたのです。
私たちが神の許に憩う安息日の祝福は、このイエス様の十字架につながる激しい愛によって私たちにもたらされました。イエス様の愛は、私たちの目を、救いを必要としている隣人へと開きます。ご自身を犠牲にしてでも救いを必要としている人を癒されたイエス様の激しい愛を、この一年も受け止める年にしたいと思います。