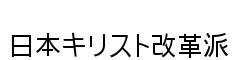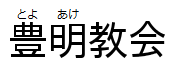2017年7月9日「神に立ち帰る」(ルカ15章11-32節)
この箇所は「放蕩息子のたとえ」と言われる箇所ですが、今日は最初に出て来る弟息子の話から御言葉に聞いていきます。弟息子は、お父さんに自分が相続することになっている財産を今欲しいと求めました。そして彼はもらった財産をすぐにお金に変えて家を出て行きました。何不自由なく父の家で暮らしていた彼は、早く家を出たいという思いを募らせていたのでしょう。
家を飛び出した彼は遠い国、父の目の届かない所、誰にも束縛されない所へ出て行き、そこで放蕩の限りを尽くしました。この弟の生き方は、自分の持っているもの、お金、才能、健康・体力、若さなどいろいろありますが、それを使って自分の楽しみを満たしていく生き方です。この息子の場合はお金がたくさんありましたから、それを使って遊びほうけたのです。遊びほうけるといってもお金があればよいわけではありません。体も元気でなければ遊ぶことも出来ません。しかしその元気も含めてどれも消耗すればなくなるものばかりです。お金だっていくらあっても使えばなくなります。しかもこの弟息子は使うことばかりで稼ぐことをしていないのですからなおさらです。
そしてすべてを使い果たしたところでおりわるく飢饉がきて、誰もが食べることに困るような事態に陥ります。お金がある時には一緒に遊んだ仲間も、お金のない彼を相手にする人はいません。まして彼を雇って面倒を見てくれる人はいません。彼は独りぼっちで放り出されます。そうなって彼は世間の冷たさ、人間関係のうつろさ、そんなことを初めて味わうことになります。華やかな時があっただけに余計に惨めです。行き着いたのは豚の世話係です。当時ユダヤでは豚は汚れた動物とされ、その世話は奴隷がさせられる仕事でした。ですからこれは最低の生活になったということです。しかも彼は豚のえさで腹を満たしたいと思ったほどでした。
自由だと思って放蕩の限りを尽くしていた彼は、自分の欲の奴隷、思い通りに生きたいという欲求の奴隷でしかありませんでした。お金のある時は喜んでついてきた人たちも、いざとなれば誰も助けてくれません。そんな中で彼は自分をどうすることも出来ませんでした。彼は全然自由ではなく、むしろ奴隷に過ぎなかった、満たされていたようで満たされていなかったのです。彼はここに至って、父の財産を湯水のように使っていた自分は、欲しいものを手に入れていたようで、実は何も得てはいなかったことに、いやおうなしに気づかされたのではないでしょうか。
こうして何もかも失って初めて彼は思い出します。自分が飛び出してきた父の家のことです。あそこには大勢の雇人がいて、ありあまるほどのパンがあるのに、自分はここで飢え死にしそうだと言います。「我に返って」とありますが、これは自分が何者か、本来どこにいるべき者か、ということに気が付いたということです。自分はあの家にいて初めて生きることが出来る、そのことにようやく気が付いたのです。彼は、あの父の家こそ自分が帰るべきところ、あそこへ帰ろう、そう思って歩き始めました。ただ、今更息子として入れてもらう資格はないので、自分の罪をお詫びし、雇人の一人にしてください、そう言おうと考えました。
ところがお父さんは、ぼろぼろになって汚い身なりで家に近づいてくる息子を、まだ遠くはなれていたのに、それが我が子だとすぐに見分けて走り寄って首を抱き、接吻して迎えます。息子は道々考えて来たわびの言葉を言い始めますが、お父さんの方はそんなことは聞かずに、すぐに迎え入れたのです。
ここで「憐れに思い」とありますが、これは相手の痛みを自分の痛みとして受け止めて揺さぶられる程の強い心の動きを表しています。お父さんは弟息子が出て行ってから毎日、息子のことを心配していたに違いありません。子どもを愛する親なら、例えば子どもが独り暮らしを始めれば、どこで何をしているか分かっていても、毎日思っているものではないでしょうか。今頃何をしているか、学校は、仕事は、人間関係はうまくいっているか、風邪をひいたりしていないか、今度はいつ帰るか・・・。子どもの方はそれほどでもないことが多いのかもしれませんが。まして、まだ独り立ちするのは早いから、というのを聞かずに家を飛び出していった息子です。財産をもらってさっさと金に換えて出て行く、これはもうお父さんをいらないと言って捨てたということです。お父さんには相当な心の痛手だったはずです。しかしそんな息子の事をこのお父さんは思い続けたのです。まだあの子は自分のことがよくわかっておらず、世の中で独り立ちしてやっていくことはできないだろう。お金を持っているから周りからちやほやされていい気になって騙されて、行き着く先は・・・。親の目にはそれが見えるのです。それでも息子が我に返って、家に戻ってくるのを毎日あきらめずに待っていたに違いありません。だからこそ遠くから見分けて駆け寄ることができたのです。
イエス様は、このような子を思う父親の愛になぞらえて、神様の愛がどんなものかを私たちに話して下さっています。このお父さんの迎え入れ方はどうでしょうか。息子が考えたおわびの言葉には、それなりの手順を踏んでから、という意味がありました。なにしろひと財産食いつぶしたのですから。お父さんにとっても、雇い人として半年か一年使ってみて、反省のほどを確認してから、というのが筋ではないかと思います。そうでなければご近所や、ほかの雇い人たちにもしめしがつきません。それが世間の常識というものでしょう。
ところがこのお父さんはそんなことは全部飛び越えて、無条件に彼を迎え入れています。しかもその待遇はというと、一番良い服(裾の長い最上の着物、しもべは着られない、自由人も祭や祝いなど労働から解放されたときにだけ着ることができる)、くつはこの場合は最上の履物、これも奴隷ではなく自由人だけがはくことができるものです。指輪は判を押すのに使う、封印するのに用いることがある権威のあるもので、息子だけが父親から授かることができたものです。そして、肥えた子牛をほふっての宴会は喜びの宴です。つまり出ていく前よりももっと高い地位につかせたと言ってもよいのです。全く無条件に、手放しで、大喜びで迎え入れる愛です。これは世間の常識からはまったく納得できないことです。
しかしイエス様は、このお父さんの迎え入れ方に、神様が、私たち人間を迎え入れる愛があるとおっしゃっているのです。自分を捨てて出て行った息子の帰りを心痛め心配しながら待ちわび、帰ってきたら無条件に赦して迎え入れる。このような常識では考えられない神の愛があなたにも必要だし、そこに私たちが帰るべきところがある、そうイエス様は語っておられるのです。
なぜ彼はこのように受け入れられたのか、なぜ父親はこのような息子を迎え入れ、宴会を開いたのか。それはお父さんが弟息子を愛していたから、彼が帰って来たのを喜んだから、というほかありません。
24節で父親はこう言っています。「この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ」。家を出て行く時、この息子は父親などいらない、死んだも同然だと思っていました。こんな家に用はないと思っていたのです。しかし今彼は、自分がこの父の家にいるべき者、このお父さんのもとでこれまでどんなに豊かに支えられ、愛され、育まれてきたかを心の底から知るようになりました。死んでいたのは弟息子の方でしたが、それがこうして生き返りました。ですから元のさやに納まったということではないのです。だからお父さんは喜んで迎え入れて宴会を開いて喜ぶ、それ以外にありませんでした。
では彼が食いつぶした身上、父の受けた傷、それは誰が償うのでしょうか。その損害は、このお父さん自身がすべて引き受けたのです。イエス様はこのようにしてご自身がこの地上に来られた意味を語っておられます。神様はこの弟を見て憐れに思い、自分自身がはらわたをえぐられるような思いで弟息子が持っていた悲惨と惨めさを引き受けてくださいました。それがイエス様の十字架です。イエス様の悲惨な十字架刑は、人間が抱える孤独と死、悲惨さ惨めさを、神様が背負って下さったことを表します。それはボロボロになって帰って来た弟息子をそのまま抱きしめる神様の姿でもあるのです。
クリスチャンというのは、どういう人がなるのでしょうか。宗教的な人、何か志があって、立派な人がなるのでしょうか。そういうことではありません。自分にはこの走り寄る神様の愛が必要なのだということを知った人、思い知らされた人、それがクリスチャンです。教会はここに描かれた神様の愛によって生き返った喜びを共にするところです。この私を神が愛し喜んで下さっていること、お互いが神の愛に生かされている事を喜び祝う場所、それが教会です。ですからこの礼拝は喜びの祝宴なのです。教会は堅苦しい所などと思わないで、これからも帰るべき所に帰って、礼拝に集い続けて神の許に立ち帰る喜びを共にしましょう。「食べて祝おう。この息子は、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ」。
主イエス・キリストの父なる神様。あなたが私たちをどれほど愛しておられるかを、私たちは知りませんでした。自分のしたいことができればそれでよいと考え、あなたから与えられたものをひたすら使い果たすような人生を積み重ねておりました。しかしそのような私たちをあなたはひとときも忘れることなく、待ち続けてくださいました。あなたから離れていた自分に気づかされ、あなたのもと立ち帰らされ、走り寄って迎えてくださるあなたの愛を受ける喜びを、生涯味わわせて下さることを感謝します。